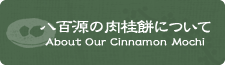鎌倉時代、和泉・河内・摂津の3国が接するところ「堺荘」として、書物に記されたのが始まり。 室町、南北朝時代、堺浦は足利幕府の遣明船の発着港となりました。
戦国乱世の時を経て、安土桃山時代、明国琉球との交易から、オランダ・ポルトガル・ルソンとの交易、 「黄金のジパング」の商港。「堺の町ははなはだ富裕にして大なる商人多数あり、ベニスの如き政治が行われている」 ―イエズス会宣教師・ビレラ
ヨーロッパの国々では、「東洋のベニス」と呼称されるほどの町として、華やかな、 繁栄の日々を送っておりました。
その頃、堺の材木町にて八百屋宗源は、貿易商人として、中国・ルソンなどの南方の諸国から、 何百種もの香料・香木を輸入し、日本全国に商っておりました。
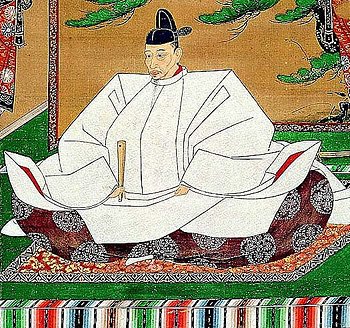
豊臣秀吉
その香料の中で「肉桂」(シナモン)は、香りもよく珍重されておりました。 しかし、香りは良いけれど辛味と苦味はとても子供や婦人には受け付け難いものでした。 八百屋宗源は一考し、つき上げたお餅に「肉桂」を混ぜ合わせたところ、大変香りも味も良い餅に仕上がり、 堺の名物として秘かに商われるようになりました。これが「肉桂餅」の始まりと伝わっております。
豊臣秀吉による大阪城の築城、それと共に八百屋宗源は堺より大阪へ店を移し、貿易商人として活躍しました。
浪速のことも夢のまた夢……
大阪夏の陣・冬の陣・そして堺の街の焼き打ち、宗源の夢も露と消え、その後の足跡も消えてしまいました。
そして徳川の世、上方文化も華やかな元禄の太平の時代、慎ましく生きて来た八百屋宗源の子孫は、 堺の地に菓子商を始め、その名も「八百源」と名のりました。家伝の菓子として伝わった「肉桂餅」、 その初代は「肉桂」を柔らかな求肥に練り混ぜ、小豆のこし餡を包み、新しい菓子として販売しましたところ、 時代と共に堺の町衆の間で評判を呼び、堺の銘菓として好まれるようになりました。
明治維新、またも堺を焦土と化した太平洋戦争…………
幾多の苦難を乗り越えて、現在、当主で6代目となっております。